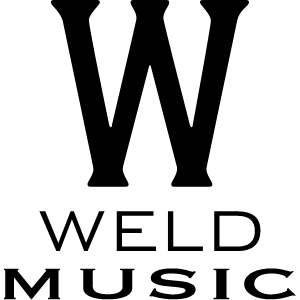2024年は、叩いても叩いても開かない扉の前で地団駄踏んでるような年だった。
ずっと一人っきりで創作に明け暮れてきた中で、また疼き出したバンドへの欲求に
新たな変化を期待して始めたThe DOJINだったが、やればやるほどにチグハグしていった。
虚しさと、悔しさが心の底に沈殿しているようだった。
人と何かをする楽しさを知っているからこそ、そこに何かが生まれる瞬間をまた味わいたいと願う。
ただ、目的や思い描いているものがすれ違えば、それは得られない。
今の自分にとってバンドというものが高いハードルであるかのような現実がそこにはあった。
ただただ、純粋に人と音楽を通して響き合い自分たちの音を生み出したかっただけなのだが、何だかんだとどうでもいいことに行く手を阻まれ意欲は消え失せ泥のような嫌な疲れが心と身体に絡みつく。
ただ一つ、今も変わらず自分の中に残ったのはThe DOJINというイカしたネーミングと描いた骸骨のトレードマーク。
次はここから始めようと思う。
湧きあがる衝動の赴くままに純粋に響く音楽をみんなに向けて放ちたい。
それだけが望みなのだ。
そんな失意の中2024年は終わり2025年を迎えたが、まだThe DOJINにはあと数本のライブスケジュールが残されていた。
もちろん、ベストを尽くすのみ。
2月26日、 俺のホームグランド「晴れたら空に豆まいて」にてThe DOJINの1stシーズンはあっけなく終わった。
前置きが長過ぎたようだが、ここからが未来へ向かう話。
去年、せっかちな俺は無謀にもThe DOJINのアルバムレコーディングのために2月初旬にスタジオを5日間おさえていた。
バンドの状況的に見ても、レコーディングしたって何も生みだせないだろうと思いメンバーには中止することを伝えスタジオのスケジュールはそのままにしていた。
そのレコーデイングスタジオは群馬の高崎にあり、選りすぐりの機材を揃えていて環境は申し分ない。
まぁ自分次第だが、そこでならきっと思い通りの響きが録れるだろうとずっと考えていた。
碌にアイデアも曲もなかったが、スタジオに入れば何かしらきっと生まれるだろうという予感めいた根拠のない自信だけはあった。
ストレスの先にはそこから解き放たれたいという欲求がある。
それが創作へと向かわせるのだろう。
レコーディングエンジニアには今、最も信頼を置いているMokyことTanizawa Motokiに依頼した。
そして今回はゲストを二人招いていた。
昨年、Mokyから紹介を受けたSaxophoneプレイヤーのIkemura Marinoと以前からの知人であったソングライターの加藤リーヌをレコーディング4日目にセッションする予定でソロレコーディングは始まった。
まずは、Mokyと二人で思いつく限りの楽器や機材をフロアーに運び入れ、いつでもインスピレーションが湧いた時に演奏できるようにセッティングした。
何もなかった広いフロアーはあっという間に機材で満たされ俺はすぐにでも音を響かせたいと気持ちが急ぐ。
まずはベースを手に取りグッとくる響きを探し、それが定まったところで思うままに弾き始める。
スタートの合図もないまま始まった演奏をタイミングを見計らいMokyが録音を始める。
もちろん場合によりけりだが、優れたエンジニアには説明などされなくともアーティストがしたいことを感じ取れる感が備わっている。
Mokyはそういうセンスを当然のように持っている。
音に対しての捉え方がとてもシンプルでナチュラル。
だから嘘もまやかしもない。
俺が彼を信頼している所以は音楽制作をする上で、おざなりにされがちな一番大切な意識をブレずに持っていることなんだ。
だから心置き無く音楽にのめり込める。
俺の場合、弾き始めの1音はそれで全てが決まると言ってもいいくらいにとてもデリケートな瞬間なのだ。
そのタイミングは静寂の中から自ら掴み取っているので、すでに音が鳴る前から音楽は始まっているということになる。
いつからか、ごく自然に当たり前のようにそれが俺たち二人のレコーディングスタイルになった。
それを黙々と3日間続け、9曲分の素材ができた。
4日目、マリノちゃんと加藤リーヌが到着。
実は、マリノちゃんは宮古島出身でDOJINがライブをした時にわざわざ帰省がてら観に来てくれていた。
その時はまだソロレコーディングすることは考えていなかったので、機会があればセッションしたいという話で終わったのだが、その後レコーディングを決めた時には、真っ先に彼女のイメージが湧いた。
普通なら彼女がどんな演奏をするのか?気になりリサーチするのだろうが、それをまったくせず何も知らぬままにセッションすることを望んだ。
Mokyが俺に合わない人を紹介するはずがないと勝手に思い込んでいた。
加藤リーヌには1曲だけ事前に音源を送り、歌のアレンジを託していた。
そもそも加藤リーヌと知り合ってから長いのだが、彼女が歌を唄うと知ったのはつい去年のこと。
DOJINのライブをスタッフとして手伝いに来てくれた時に彼女からソロアルバムCDをもらって初めて知った。
聴いてびっくり。
彼女の歌声に惹きつけられた。
すぐに、自分の曲で歌ってみないかと誘ってみたら、是非やってみたいと言ってくれIphoneで録音した音源を送りアレンジを頼んだ。
そんな二人とのレコーディングはまさに奇跡だった。
まずは、加藤リーヌが唄う曲の構成を音を出しながら30分ほど簡単に打ち合わせ、すぐに1stテイクをレコーディングした。
何一つ迷いなくお互いを感じ合い心が溶け合うようなセッション。
コントロールルームで再生してみるとその響きに心が震えた。
その後2ndテイクを録ってみたが、!stテイクほどの魔法は起きなかった。
二人とは初めてのセッションなのだが、ほとんど前置きもないままにここまで共鳴し合える人には未だかつて出会ったことがない。
その時感じたのは、神に祝福されたような愛とすべてが許されたかのような解放感だった。
予定では、加藤リーヌはこの1曲だけで終わりだったのだが、この機会を無駄にする訳にはいかないと思い、即興でもう1曲セッションしようと提案した。
いきなり即興でベースをループさせセッションが始まった。
その時、俺たちは無敵だった。
きっと、やればやるだけ曲が生まれただろう。
でも、欲張っちゃいけない。
そのセッションで役目を果たし、加藤リーヌはスタジオをあとにした。
その後、前半の3日間で録った素材の中から数曲選びサックスのダビングをした。
とても不思議に思ったのは、宮古島の風土からこんなにも洗練された旋律が生まれるのか?ということ。
そして、彼女の素晴らしさは人の響きから魂の声を感じとり、その声に答えるようにサックスを吹けるということ。
彼女とセッションしていると、音楽という見えない世界の中でこそ感じられる特別な感覚になる。
最終日はさらに即興で曲を作り、マリノちゃんとダビング作業をしてレコーディングを終えた。
このレコーディングで俺が得たものは大きい。
それは二人の才能あふれる女性たちから授けられた。
そして信頼し合えるMokyの存在がこのレコーディングを楽しませてくれた。
俺たちが過ごした5日間の魂の記録はアトリエのある香川へ持ち帰り、そこでじっくりと仕上げる。
その響きの生々しさ、美しさ、激しさを損なわぬよう大切に扱いたい。
香川でのMIX作業はスタジオでDAWソフトにレコーディングされた音を一旦アナログミキサーに立ち上げMIXを行い、それをまたDAWソフトにレコーディングするという何とも今時、面倒だと思われるような方法で行っている。
その理由は、「その音が好きだから」である。
アナログを経由するだけで音の質が変わる。
せっかく立派なスタジオで高価なマイクで録った音を少しも損いたくはない。
俺が使っているアナログミキサーは90年代に生産されたものでネットオークションで低価格で手に入れたポンコツだが、幸いにも近所にアナログ機材専門でリペアをしてくれる貴重な人がいてくれるおかげで騙し騙しだが何とか使えている。
一度、オーバーホールを見積もってもらったのだが、買った値段の10倍以上はかかってしまうと言われた。
しかも、録音されたチャンネルに対してチャンネル数がまったく足りないたった10チャンネルのミキサーだが、パソコン画面で見るよりも音がよく見え臨場感がある。
ただUndo(やり直しが)ができないので一度バラしてしまったら、また1からやり直さなければいけない。
使い始めた時はそれが大変で嘆いていたが、慣れてくるとそれが利点に思えてきた。
いつもフレッシュな気分で始められる。
ビートルズの頃はたった4チャンネルしかないのにあんな素晴らしい音楽を生み出している。
そこには、限られたシステムの中で工夫するという行為によってもたらされる効果は絶対にあると思う。
そんな機材を使い毎日黙々とMIXした。
Mokyにアドバイスをもらいながら、何度も何度もやり直した曲もある。
そしてついに、完成!
マスタリングはこの作品をレコーディングしたMokyが適任だと思いお願いした。
タイトルはこのレコーディングで体験したあの瞬間を思い、
「確かに今、そこにある愛と呼べるもの」とした。
そこから連想したイメージでジャケット用に絵を描いた。
今まで一人で作り上げてきた作品とは、明らかに違う。
それは自分以外の人たちが、俺の世界を受け入れ応えてくれたことに他ならない。
そこにはきっと愛がある。
The DOJINでは成し遂げられなかった音楽はここにあった。
今思えば、2024年の困難がなければこのアルバムは生まれなかっただろう。
生まれる理由があったからこそ生まれた、そんな作品です。
追伸
昔はアルバム発売すると取材を受け、決まりきったことばかり聞かれウンザリしていたが、今はこうやって伝えたいことを自分で発信できる。
それは、大変喜ばしいことだ。
照井利幸